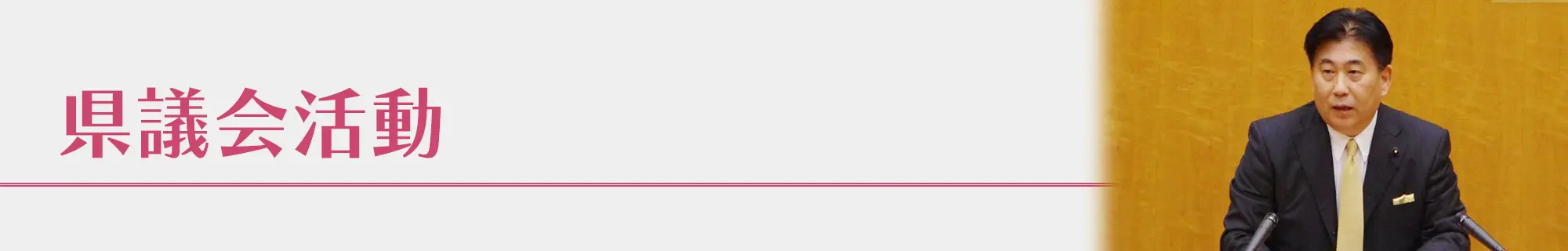

令和6年総務企画委員会 2024年10月4日
【富田昭雄委員】
木藤俊郎委員からも、南海トラフ地震臨時情報の話が出ており、少し機運が高まっている中、国が被害想定の見直しを行う動きがあるようだが、それを受けて本県も見直しを行うと聞いている。今回見直しを行うのはなぜか。
【防災危機管理課担当課長(政策・啓発)】
国は、南海トラフ沿いで想定すべき最大クラスの地震・津波に対する被害想定を、2012年8月に1次報告として建物被害、人的被害を公表し、2013年3月に2次報告として施設被害、経済被害などを公表した。その被害想定に基づいて、2014年3月に南海トラフ地震防災対策推進基本計画を定め、計画期間を10年として地震防災対策を推進してきた。今年度、この計画期間の終期を迎えることから、防災対策の進捗を確認するためのフォローアップと、次の目標を定めるために、昨年から新たに被害想定の見直しが始められているものである。
【富田昭雄委員】
見直しをしながらも計画をつくるためかと思うが、今回の被害予測調査に関して、国のガイドラインは示されているか。
【防災危機管理課担当課長(政策・啓発)】
今回の調査に当たり、国からガイドライン等は示されていない。国の被害予測調査の見直しの検討は、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ及び南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会で行われている。本県としては、これらの検討状況などを注視し、参考にしながら被害予測調査を実施していく。
【富田昭雄委員】
ガイドラインが示されない中、県独自で被害予測調査を行うとのことだが、その意義はどこにあるのか。また、他県の状況はどうか。
【防災危機管理課担当課長(政策・啓発)】
国の被害予測調査の手法を基に、ゼロメートル地帯での浸水被害など、本県の地域特性を踏まえた被害想定を行う必要がある。また、国の被害予測調査結果は市町村単位での被害量を公表していない。市町村単位の詳細な被害量は、具体的な対策を実施するために必要であることから、県においても調査を実施する必要がある。また、他県の状況としては、静岡県や三重県、和歌山県などの南海トラフ地震防災対策推進地域指定市町村を有する県では、本県と同様に県で被害予測調査を実施していくとのことである。
【富田昭雄委員】
その調査の内容だが、具体的に10年前と同じようなことをやるのか、何か違うのか。
【防災危機管理課担当課長(政策・啓発)】
被害想定としては、南海トラフで実際に発生した過去の地震規模を重ね合わせた過去地震最大モデルと、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの理論上最大想定モデルの二つのモデルについて、振動や液状化、崖崩れ、津波などを予測する。この地震動や津波などに伴って発生する人的被害や建物被害、ライフライン被害、火災発生、避難者数などの調査項目を市町村単位で予測する。
10年前の被害予測調査との違いは、前回の調査以降に公共工事などで新たに得られたボーリングデータなどを用いて、全県域で新しい地盤モデルを構築する。その地盤モデルを活用して、より精度の高い被害予測を行う。さらに、この10年間の建築物や堤防の耐震化などハード対策の進展状況や、最新の人口分布などを用いて、より実態に即した被害予測を行う。また、前回の調査からの変更点は、新たに平成28年熊本地震や令和6年能登半島地震において課題となった災害関連死についての被害予測を実施する。
さらに、前回の調査地震モデルは、南海トラフを震源とする巨大地震が一度に発生するという想定となっていた。しかし、過去の事例では1854年の安政東海地震、安政南海地震が約32時間の間隔をおいて発生したこと、1944年の昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震が約2年間の間隔をおいて発生したことなど、南海トラフの東側と西側において時間差で地震が発生した事象があることから、時間差発生地震についても被害予測調査を実施する。
【富田昭雄委員】
調査結果はいつ発表されるのか。
【防災危機管理課担当課長(政策・啓発)】
今年度と来年度の2年にわたって調査を実施し、2026年6月頃に開催予定の防災会議での公表を予定している。
【富田昭雄委員】
2年もかかるのか。
【防災危機管理課担当課長(政策・啓発)】
今年度は地震動などの計算をするために、公共事業などにおいて実施しているボーリングデータを収集し、新たな地盤モデルの構築を行う。また、人的被害や建物被害、ライフライン被害、火災発生、避難者数などの予測を行うために、建物に関するデータや人口データなどを収集し、250メートルメッシュごとにデータを整理するなど、被害予測に当たっての準備作業を行う。来年度は、今年度の調査結果及び収集したデータを基に、人的被害や建物被害、ライフライン被害、火災発生などの要素を予測し、被害を算出する作業に1年を要することから、2年の調査期間が必要となる。
【富田昭雄委員】
時間がかかることはよく分かった。では、調査結果の活用方法を伺う。
【防災危機管理課担当課長(政策・啓発)】
今回実施する被害予測調査の結果から得られた課題や対策は、本県の地震防災対策に反映し、充実強化を図っていく。また、地域特性を踏まえた市町村ごとの詳細な調査結果を示すことにより、市町村及び防災関係機関の地震対策に広く活用してもらい、県全体の地震対策の推進につなげていく。さらに、県民自らが防災対策を進めるための参考資料として活用することができるよう、ウェブサイトなどにおいて調査結果を公表する。
【富田昭雄委員】
時間をかけて相当な労力で人を集めたスタッフが調査することになるが、被害予測調査を作って終わりではないため、あくまでデータを集めることによって被害想定し、少しでも減災させることが大事である。いかに防災計画につなげていくかを、今から考えて計画をつくってほしい。2年の調査をしてる間に大地震が起きるかもしれないので、悠長なことを言ってられないが、南海トラフ地震の場合は相当大きな被害が出ると言われているため、どう未然に防ぐか、しっかりと対策を組み、どう県民に周知するのか、市町村とどう連携して対策を打つのか、今から検討することを要望する。

