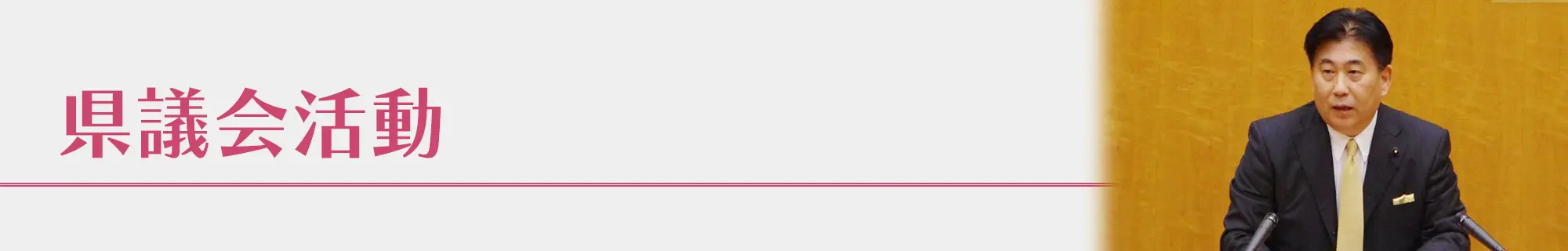

令和6年総務企画委員会 2024年12月13日
【富田昭雄委員】
次期行革大綱の策定が大詰めだと聞いたため、DXに伴う行革の進捗状況について伺う。
東京都が出しているシン・トセイに、行革の様々な計画が載っていたため、これを調べたところ、東京都は、都政のクオリティ・オブ・サービス(QOS)を向上させるために、DXをてこにした都政の構造改革に取り組んでいるとのことである。これが非常に分かりやすく、一つ目は仕事の進め方やオフィス環境の問題、二つ目は職員同士のコミュニケーション、上司、部下のコミュニケーション、また都民とのコミュニケーションをデジタル化によって進め、改めて都政のQOSを向上させるとのことである。
そこで、最初に出てきたのが、オフィスの環境を変える意味で、道具を変えることが一番良いため、五つのレスがあり、ペーパーレス、FAXレス、はんこレス、キャッシュレス、行政手続のタッチレス、この五つのレスを進めているとのことである。
併せて、仕事上でこれらの目標を数値化することが見える化も含めて必要であり、数値も出ていた。コピー用紙の調達量は、2016年との対比だと、現在、70パーセント削減されている。ファックスに至っては、対2019年比で99.1パーセントまで削減されている。まだ私の事務所にはファックスがあり、議会事務局からもファックスによる通知が送られている。答弁を求めることはないが、議会事務局長はこうした現状を知っているか。東京都では、FAXレスの実施により99.1パーセントが削減されている。はんこレスについては、電子決裁率が昨年度末で99.8パーセントと聞く。キャッシュレスについては、2022年3月で全78の都立施設において導入されている。タッチレスを進める行政手続のデジタル化は、昨年現在、2万8,000プロセスのうちの69.97パーセントがデジタル化されているとのことである。
この取組目標は非常に分かりやすいと思うが、これら五つの取組について、本県はどれぐらい進んでいるか。
【総務課担当課長(行政改革)】
まずペーパーレスだが、高機能の大型ディスプレイやタブレットを導入、活用し、会議における配布資料の減量化を推進している。用紙購入量は昨年度、全庁で1,690トンであり、5年前の2018年度と比較して8パーセント減少している。
ファックス通信については、受信印刷枚数の多い所属の洗い出しを進めており、今後ファックスの使用により非効率となっている業務を対象に、メールなど他のデジタルツールへの置き換えを推進していく。併せて、ネットワークファックスの活用により、情報漏えいリスクの軽減や効率化、ペーパーレス化を図る。
はんこレスについては、2020年度に行政手続の実態調査を行い、県が押印を求めていた4,760種類の行政手続において押印を廃止した。また、電子決裁率は昨年度で88.6パーセントである。
キャッシュレスについては、昨年4月からオンライン申請を伴う収納などにキャッシュレス決済を導入しており、県施設の窓口においても順次導入を進めている。窓口で使用料等を徴取する公の施設は49施設あるが、昨年度までに88パーセントに当たる43施設で導入済みとなっている。
最後に、行政手続のオンライン化によるタッチレスは、申請数が極めて少ないものや、複雑な審査を必要とするなど、オンライン化が困難なものを除き、来年度までに順次オンライン化を進めることとしており、昨年度末時点で1,212手続、年間処理件数では全申請の65パーセントに当たる約414万件がオンラインで申請されている。
【富田昭雄委員】
まだ少し甘い。特にコピー用紙は8パーセント削減とあるが、ぜひ進めてほしいと思うし、数字もしっかりと把握してほしい。
次に、次期行革大綱で掲げる三つの改革の視点の一つに、DXのさらなる推進があるが、どのような進捗目標、数値目標を設定して、見える化しようとしているのか伺う。
【総務課担当課長(行政改革)】
次期行革大綱の素案では、現行のあいち行革プラン2020と同様、取組の進捗状況を体系的に把握するため、三つの改革の視点を踏まえた取組がどの程度達成されているかを表すものとして、三つの視点にそれぞれ10項目、合計30項目の進捗管理指標を設定している。
また、進捗管理指標のうち、特定の値の達成を目指して計画的に取り組むことがそれぞれの改革の視点の一層の進捗につながると考えられる15項目について、数値目標を設定している。
このうち、DXのさらなる推進の視点においては、RPA及びノーコード・ローコードツールの活用数、生成AI活用職員数といった庁内業務の効率化、高度化に関する指標や、行政手続のオンライン申請率、電子契約サービスによる契約件数といった行政サービスの向上に関する指標などを設定している。
また、デジタル人材育成研修の延べ受講職員数や用紙購入量などの指標については、数値目標を設定しており、進捗状況の見える化を図りながら、目標達成に向けて、デジタル人材の育成、ペーパーレス化の推進などの取組を計画的に進めていきたい。
【富田昭雄委員】
次に、シン・トセイが掲げるもう一つの取組である、部門や役職を超えての職員同士の意見交換やコミュニケーションについて、特に若手がアイデアを提案し、課題解決で議論したりすることは非常に重要であり、また、部門長が部下に自分の考え方や仕事のやり方を発信していくことも大変重要なことだと思う。
こうしたことを、東京都はデジタル提案箱やQ&Aフォーラムなどを、ポータルサイト上に立ち上げながら意見交換を行っているが、本県においては職員同士の提案や要望を投稿できるような仕組みはあるか。
【DX推進室長】
本県においても、職員がデジタル化・DX推進に関する提案や相談を投稿できるデジタル改善目安箱を本年10月21日から設置、運用している。この目安箱に投稿できる内容は、デジタル技術を活用した業務の効率化・高度化に係る提案や相談、既存システムに係る改善提案、その他デジタル化・DXに係る意見・提案である。投稿に当たっては、上司の許可を得る必要はなく、全職員を対象にポータルサイトから直接投稿することができ、目安箱の設置から約1か月を経過した本年11月末時点で132件もの多くの投稿があった。
投稿された提案や意見は、デジタル戦略監をリーダーとし、各局等に配置したデジタル化・DX推進担当を構成員とするデジタル化・DX推進チームにおいて共有し、提案先となる所属とともに対応の検討に着手している。
【富田昭雄委員】
職員からの提案があったとあるが、具体的にどのようなものがあったのか。
【DX推進室長】
具体的な投稿について、初めに、デジタル技術を活用した業務の効率化・高度化に係る提案や相談では、勤務時間や休暇、旅費や通勤手当等の服務関係の諸規程について、問合せ用のチャットボットを作成することで、服務担当職員の業務の効率化につながるという提案、また、地方機関の職員が集まる会議について、オンライン会議の利用をルール化し、移動時間等の負担の軽減を図りたいといった投稿などがあった。
次に、既存システムに係る改善提案では、ネットワーク通信の快適性を求めるものや、メールやチャットといったグループウェアの操作性の改善に関する投稿などがあった。
最後に、その他デジタル化・DXに係る意見・提案では、デジタルツールの使用方法や各課の先進的な取組事例を庁内に紹介してほしいといった投稿などがあった。
改善につながる提案や意見は、投稿者に改善等の取組内容を回答するとともに、優れた改善内容を全職員に周知することで、業務改善につながる提案を促進していきたい。
【富田昭雄委員】
現在のデジタル改善目安箱は、恐らく、提出された意見がデジタル化・DX推進チームに上がってくるといった方法だと思う。そうした意味では、例えば相互に意見交換ができたり、上司が部下に意見を聴いたり、県民から意見を聴いたりする仕組みには至っていないと思うが、どうか。
【DX推進室長】
デジタル改善目安箱は、双方向のコミュニケーションが取れる仕組みはない。県民からの提案は、デジタル改善目安箱とは異なるが、県政全般にわたってインターネットで受け付けている、県政への御提言という仕組みがある。
【富田昭雄委員】
ぜひ東京都のシン・トセイも参考にしてほしい。行革を行う上で、上司がどういったことを考えているかを部下に示す、発信することも必要であり、実際に提案したものや課題解決に関して相互にいいねボタンを押すことや、簡単に書き込みや追記ができたりするような仕組みも必要である。県民が、県庁内で行われている取組について、随時意見ができるようなものがあってもよいと思う。これは、まさにデジタル化をてこに、開かれた組織、フラットな組織、また、行革そのものを進めていく大きなてこになると思うため、よりフラットな組織で、要望がいえる仕組みづくりを目指してほしい。
最後に、デジタル戦略監に質問する。デジタル化の取組について、例えば、議員に対する答弁検討に関して大きな画面を導入したことで簡単に行えるようになった、生成AIのガイドラインを改定したなど、様々なことを行っていると聞く。今後、DXにより愛知県庁全体のサービスを向上していこうとする中で、考えを伺う。
【デジタル戦略監】
仕事の進め方や数値化、コミュニケーションについて問題提起があった。
まず、次期行革大綱の素案では、先ほど答弁があったように、DXのさらなる推進を改革の視点の一つとしており、デジタル技術を積極的に活用し、県の業務やサービスを変革することで、それらをより効率的・効果的に実施し、県行政の質の向上に取り組んでいく。
具体例として、委員から話があったように、新しい道具である生成AIを活用した業務の高度化・合理化や、デジタル技術の活用による柔軟な働き方の推進等について、次期行革大綱に位置づけた上で取組を加速していく。
また、次期行革大綱の推進に当たっては、現行のプランと同様に、副知事をリーダーとするPTにより進捗管理を行うが、新たに私がサブリーダーの一人に指名される予定となっていることは、今定例議会の本会議代表質問において知事から答弁した。私もこのPTの一員として、富田昭雄委員から話のあった、仕事や進捗状況の数値化、見える化にしっかりと取り組んでいく。
さらに、もう一点のコミュニケーションについて、私自身が様々な問題意識や提案を多方面の職員から提示をされ、それが端緒となって業務改善につながった経験がある。
この経験から、デジタル改善目安箱については、本年4月に立ち上がった、私を含む56人からなるデジタル化・DX推進チームで構想を練ってきた。ここで、先ほど話のあった大画面による答弁検討等も実施されることとなった。
このチームは、各局の若手担当者から職種を問わずに選任しており、デジタル技術に慣れ親しんだ世代から現場に近いところで業務の効率化・高度化に積極的に取り組んでいる。
ただ、このチーム以外の若手職員にも、日常の業務の中でデジタル化に対する熱い思いや斬新なアイデア、関連する問題意識を多く持っていると思い、それらに耳を傾け具現化する仕組みを作ろうと考えて、デジタル改善目安箱の設置に至った。デジタル改善目安箱への投稿に対しては、私も目を通し、意見を述べ、全ての投稿に対して回答することにしている。
このように、職員の負担軽減に加えて、職員の意欲増進を実現する取組を多層的かつアジャイルに行うことにより、県民や県内事業者にとって、より質の高い行政サービスを持続可能な形で提供していくことの実現に向けて、引き続き全庁を挙げてデジタル化・DX推進に取り組んでいく。
【富田昭雄委員】
デジタル戦略監を先頭に、デジタル化によって愛知県庁が大きく改善され、その取組が県民のためになるよう、要望する。

