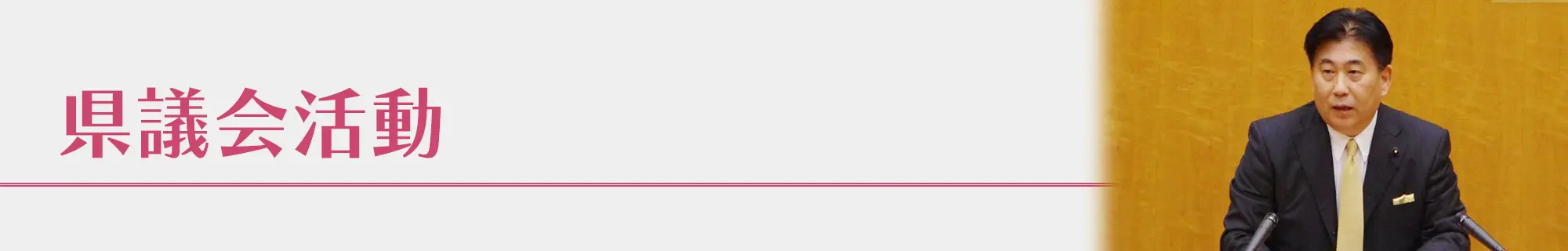

令和7年2月定例会(第5号) 2025年3月3日
◯九十一番(富田昭雄君)
議長のお許しを得ましたので、順次質問をしてまいります。
今回は私なりに重大な危機だと思っている事柄について取り上げてみたいと思います。労働問題について、教育問題について、食料問題についてお聞きしたいと思います。
まずは、労働問題については、カスタマーハラスメント対策についてお聞きいたします。
顧客による従業員への過度なクレームや理不尽な要求、いわゆるカスハラの被害が深刻化しています。最近お聞きした職場からの事例でいえば、たまたま取ったお店の電話で、なぜ割引を勝手に終了したか説明しろと二時間罵声を浴びせられ、電話が終わってから対応した女性は泣いたそうです。
このような暴言や威嚇、脅迫、長時間拘束、土下座を強要されるなど、様々な迷惑行為で従業員が追い詰められるケースが絶えないのです。職種別で被害率では、福祉系の専門職員が最も多く、顧客サービス、受付、秘書、医療系の専門職員、ドライバー、小売業の接客、サービスといった順番ですが、あらゆる職種に広がっています。
カスハラの増加がもたらす負の影響は様々ですが、最も深刻なのは従業員のストレスと離職であります。カスハラの多い職種では、従業員が苦しんでばかりいるだけではなく、人がどんどん辞めていき、採用しようとしても敬遠されて、慢性的な働き手不足となる悪循環にはまっています。早急に社会全体でカスハラを減らしていく取組をしなければなりません。
厚生労働省は、二〇二二年、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを発表しています。店員の対応が気に食わないと、店員の顔や名札を撮影し、SNSで拡散するぞと脅かす例もあり、会社や店側の名札をイニシャル表記にするなど対応に迫られ、大手飲食店も自治体も名札を簡略化する動きが広がっています。昨年は、このような動きから、カスハラをめぐるルール整備が大手企業では急ピッチに進みました。大手コンビニでも対応ガイドラインを策定し、顧客に向けて対応指針を発表しました。航空会社や百貨店でも対応方針が明らかにされています。
また、昨年は自治体でもカスハラを防ぐ条例づくりの動きがあり、全国初となった十月の東京都に続き、十一月には北海道が条例を制定いたしました。群馬県や栃木県、三重県も条例制定に動いています。先行した東京都、北海道の条例は、消費者や住民への啓発、事業者の側の対応を促す内容で、カスハラ行為への罰則導入は見送りました。一方で、実効性確保を目指し、罰則導入も視野に入れているのが三重県です。我が愛知県は、一月二十日にカスハラ防止条例検討会議が開催され、できるだけ早い議会に条例制定案を提出する意向を示されたと承知しています。
その中でも罰則規定については、カスハラの行為が限定的になり、罰に当たらない行為が正当化されるおそれがあるなどの理由から見送られる意向と聞いております。
私ども会派においては、カスハラ条例のプロジェクトチームを立ち上げ、労働団体からも意見を聴取し、議論をしてまいりましたが、やはり実効性を持たせるためにも罰則規定があったほうがよいという意見でまとまりました。今回は、まずは速やかに条例制定することを優先するなら、今後国の動きや社会的な情勢が変わった場合には罰則規定を盛り込むことも含めて見直しを行うことが視野に入っているかということであります。そして、企業がいわれなき迷惑行為に対して、出入り禁止やサービスを停止するなど毅然とした対応を行うために、根拠となる規定が条例上に欲しいと思います。ただし、同時に顧客の権利を不当に侵害しないように明記することも重要な視点と考えます。
そこでお聞きいたします。
条例制定に向けて、愛知県独自のカスハラ条例をどのような内容にされようとしているのか、お考えをお聞かせください。
また、条例制定と合わせて、県の責務として、県民へのチラシやポスターによる啓発活動や事業者による従業員の接客マナー教育や対応マニュアル作成の義務化も必要と考えます。
そもそも、なぜカスハラが増えているのでしょう。現在の日本社会の孤独、孤立傾向は理由の一つでありましょう。家族や友人と来店しているとき、あるいは近所の人など、多少なりとも知った人の目があるところでは声を荒らげる振る舞いはしにくいものです。また、スマホやSNSの普及、カスハラが発生しやすい状況をつくっているのかもしれません。今や誰もがこんな対応されましたと撮影し、SNSで拡散される環境を持っています。高齢化も主な要因の一つと考えられます。このような社会の環境変化が理由だとすれば、チラシやポスターだけで対策がどこまで機能するのか未知数であります。カスハラをするような人が迷惑行為をしている自覚があるかということであります。これからカスハラの認知が進み、具体的にどんな行為がカスハラに当たるのか社会的にコンセンサスが形成されれば改善されていくことでありましょう。防犯カメラやセルフレジが普及されればインフラの面からも抑止が進むのでしょう。
しかし、カスハラが減少する成果が得られるまでは年月がかかると思われます。すぐにでも従業員の離職を止めなければ仕事が回らなくなる現場に、それを待っている猶予はありません。急ぐべきは顧客向けの防止策をしつつも、従業員向けの防衛策であります。カスハラが起こったときの対応策を間違えないこと、従業員が安心して働ける環境をつくることです。一刻も早く実効性のある条例やガイドラインが示され、それを機に、企業での対応策や顧客への啓発活動が活発に推進されることを期待するものです。
そこでお聞きいたします。
今後どのようにカスハラ防止対策に取り組まれるのかお聞かせください。
次に、教育問題についてお聞きいたします。
最初に、愛知県のキャリア教育についてお聞きします。
附属中学を県立高校に併設する中高一貫教育が始まります。明和高校附属中学普通科コースの入学選抜では、倍率が一六・六六となるほど、他も軒並み高倍率となっています。探求的な学び、社会の課題を解き、変革を起こすチェンジメーカーの育成を掲げ、高い関心を集めているようです。公立の中高一貫校は、全国では二百十九校あり、愛知県は遅い参入ですが、二六年度までに併設型だけで九校開校する計画で、一気に全国でも一貫校が多い県になります。
こうした県立高校の急激な改革の背景には、二千七百もあった過去最多の欠員、生徒の数が十年後一万人減るという予測から改革のスピードが早まり、そこへ私学の授業料無償化で公立がやや不人気となれば変わらざるを得ない状況があると思います。
しかし、大きな変化のチャンスなのかもしれません。ぜひ改革を前に進めてほしいと思います。
あわせて、愛知県独自の公私二対一の募集比率の見直しと地域の学校の編成についても急がなければならないと思います。課題の中でも私が今回注目するのは、全日高校の実質進学率が八七%まで下がり、その分、通信制高校が伸びて、全体の八%もあることです。このうち専修学校併修を除くと、通信制だけでは三・九%ですが、この通信制の二千七百三十八人の生徒の進路を追跡できていない。把握しているのは一部の公立高校の通信制課程で、それも約半数近くの生徒が退学しています。やはりここは全容をはっきりさせる必要があると私は思います。大学進学がどんどんと助長されていく中、高校からの就職は求人が増大するものの、就職の実績は伸びず、今こそ早い段階からのキャリア教育を充実させる必要があると思います。
そういう意味で一点指摘したいのが、唯一社会を経験できる機会である高校でのアルバイトであります。今は禁止されているようでありまして、愛知県下の公立高校百六十四校をある機関が調査したところ、校則で八割以上の高校が原則禁止、もしくは許可制という結果でした。私の学生時代はバイトをよくやっていたという記憶がありますが、学校が荒れ、非行が問題になってから禁止が続いているようであります。
現在、県立のある高校ではアルバイトにおけるキャリア教育を積極的に位置づけようという動きもあり、ぜひ高校生のアルバイト禁止のルールを教育委員会の音頭で即刻見直すべきかと考えます。
その中で取り上げたいのはアプレンティスシップという制度です。訓練生という意味だそうですが、イギリスはじめ、カナダ、アメリカでも急激に広がっています。最近、皆さんも御存じのように、映画ではアプレンティス:ドナルド・トランプの創り方などに使われております。これはトランプの若かりし頃のドラマで、成功を夢見る気弱な青年実業家だった彼が、ロイ・コーンという弁護士との出会いで破天荒な人物へと変貌していくさまを描いた作品です。アプレンティスシップという選択は、将来のために企業で経験を積むけどインターンではない。お金をもらって働けどバイトではない、自分の未来を開くための新しい選択がアプレンティスシップだそうです。
私はたまたまある方の紹介で介拓奨学生プログラムという介護のアプレンティスシップに参加した高校生の発表会を見学いたしました。このプログラムは、夏休みを利用し、介護施設で初任者研修を無料で取得し、介護福祉業界で働いてキャリアを積んで、その経験を生かして進学したり就職したりするものです。
この発表会で表彰された高校生がたまたま隣に座ったので、声をかけてみました。どうしてこのプログラムに参加したのと聞いてみました。通信制高校の先生からチラシをもらい、何か変わるかなと思い、参加してみたそうです。中学は不登校で、ほとんど学校に行っていないので、通信高校に行くことになりました。だから中学、高校はほとんど学校に行かず、毎日家にいますとの返事でした。今回はどうでしたかと聞いたら、今回の経験で自分の意見が言えるようになりましたし、人と関わることが楽しいと思うようになり、介護の仕事に喜びを感じましたとお答えになりました。じゃ、将来は介護福祉業界で働くのと聞いてみましたら、心理学を学ぶ大学に行きますと。生きづらさを抱える人の役に立ちたいと思いますと答えてくれました。これには私は感動いたしました。もともと優秀な方だったと思いますが、誰かがやる気スイッチを入れてくれたのでしょう。彼女にはぜひ生徒の悩みを聞くカウンセラーになってほしいものです。
このように、高校生の段階でアプレンティスシップを導入することで学びの目的がはっきりし、学業との両立が前提の働き方ができるようになります。折しも不登校など問題が広がり、それに伴い、通信制高校を選ぶ選択をする高校生が大幅に増加している現在、昼間の時間を持て余している高校生も増えています。単に切り売りするアルバイトではなく、将来に学びと収入を両立させるアプレンティスシップの機会が増えれば、とても貴重な経験と能力向上が見込めるわけです。既にイギリスでは、高校レベルを卒業する二二%がアプレンティスシップを選択しています。高い学費も必要とせず、高い専門性が必要とされる仕事に就けると人気が高まっています。
そこでお聞きいたします。
このような新しい制度をどう捉え、愛知県のキャリア教育を今後どのように進めていかれるのか、お考えをお聞きします。
次に、高校での進路指導と大学での奨学金についてお聞きします。
日本は今、大学全入時代に突入しています。全大学の募集定員はおよそ六十二万五千人に対して、入学者が六十一万三千人と、史上初めて下回ったのです。要するに、より好みをしなければどこかに入れる状態になったわけです。大学関係者に聞きますと、すぐに定員割れが進むのかといえば、当分は大学進学希望者が多く、難関大学は今まで以上に競争が熾烈になると予想しています。しかし問題は、大学の定員割れを埋めるために、進路指導の大学偏重が進めば入学後のミスマッチが生じやすく、学生の学習意欲の低下や将来のビジョンが見いだせず、結果として大学を退学することにつながる可能性が多くなると指摘をされています。
また、大学進学の二人に一人の学生が奨学金を利用して大学に通っているということです。奨学金には給付型もありますが、圧倒的に有利子の貸付型であり、これはただの長期ローンでありました。卒業時には平均三百十万円の借金を背負い、四十歳近くまで毎月二万ずつ返済するわけであります。就職が非正規となれば家庭も持てないと嘆いている言葉が聞こえてきます。これでは少子化は止まりません。本来は国も県もあらゆる機関が給付型の奨学金を増やすことが望ましいわけでありますが、財源が限られています。
そこで指摘したいのは、現状に合った進路指導が行われているかということであります。高校生自身が自分の将来について深く考え、主体的に進路を選択できるよう、本人の意思を尊重する面談や職業見学など、様々な機会を設けることが重要です。大学進学だけではなく、専門学校、就職、留学、様々な選択肢について、高校生に情報を提供し、それぞれのメリット、デメリットを説明する進路指導ができているかということであります。今は職業観や勤労観の育成につなげることが必要だというふうに思っております。
私は、昨年十一月に大分県にあるAPUという立命館アジア太平洋大学を視察してまいりました。世界百十二か国から三千百四名、国内各地から三千二百九名が学ぶ国際大学です。副学長はじめ幹部の方と懇談をしてまいりましたが、三十年の歴史があり、世界で活躍する多くの卒業生を輩出しています。留学生のほとんどが七〇%から八〇%の奨学金を受けて、一年生は全寮制でありますけれども、二年生からは大分市や別府市で下宿し、旅館やホテル、レストランで働くそうです。まちの人口も増え、すごい労働力でありますが、お客として母国から家族や友人を観光に大分県に呼びます。大学の特性を生かした地域連携であり、画期的なまちおこしだと思います。
こうした環境を求めて日本国内各地からどうしてもここで学びたいと目的意識がはっきりした学生が集まっています。キャンパスの案内をしてくれた学生の方々も観光学部で学び、将来は旅行会社に就職したいと語っていました。このAPUの環境で学べて本当によかったと語っていました。このように自分の進路を決め、学びたいことを選択できる環境が重要であります。
また、進学する場合に奨学金を利用するかどうかも大きな決め手となる要素であります。先日、東京都は、大学卒業後に都内で教員や自治体の技術職員として就職した場合に、奨学金返済額の半分を肩代わりする制度を始めたと発表いたしております。奨学金返済支援であります。これも進路を決める大きな要素の一つになります。これは民間企業も同じでして、民間の企業が奨学金の返済を肩代わりすることをアピールすれば人材確保につながります。そのため、財源を県が支援すればより実施しやすくなるでしょう。大学生の二人に一人が奨学金を利用する時代に、これは人材確保に有効ですし、離職を食い止める手だてでもあります。今私が聞いている中小企業の経営者の悩みは、採用してもすぐに辞めてしまうということに頭を抱えているようであります。
そこでお聞きいたします。
県立高校での進路指導をどのように取り組まれているのかお聞きします。
また、教職員や県職員、民間企業の人材確保、離職防止になるような取組、特に奨学金返済を肩代わりする支援についてお聞きいたします。
次に、食料問題についてお聞きいたします。
最近、米の値上がりが止まらない。流通業界の買い付け競争が激しさを増して、新米の供給開始後も在庫不足が解消されず、店頭価格は前年比の五割以上の高値であります。昨年の米騒動も収まらず、政府もやっと備蓄米を放出する動きとなりましたが、早く米の価格が安定してほしいものです。
米ですらこのような不安定な供給状況だとすると、食料自給率三八%の海外依存の高い日本にとって、食料問題は深刻な問題です。国際紛争や気候変動によって、いつ海外から食料が入ってこなくなるのではないかと心配するのは私だけでしょうか。さらに、地球温暖化や貿易摩擦などの影響により、食料の輸入が滞るリスクも高まっています。
このように、食料を輸入する主要相手国が異常気象や自然災害に見舞われたり、紛争や政治的な理由で輸出がストップすると、日本の食料供給に直結します。また、リスクを考慮すると、国内の生産基盤を強化することが急務と考えます。
農業の生産現場に目を向けてみますと、高齢化と担い手不足が深刻な課題となっています。農林水産省の調査結果によりますと、農業従事者の平均年齢は六九・二歳に達し、農業従事者が約二十年間で半減し、減少の一途をたどっています。また、新規就農者も減少傾向にあり、次世代農業を担う後継者が確保できないため、将来的な食料生産基盤の維持が難しくなることが懸念されています。特に農村地域では過疎化と高齢化が進み、耕作放棄地の増加にもつながっています。これにより地域の農業生産力が低下し、地域経済にも大きな影響を及ぼしています。農業の担い手を確保することは、食料生産基盤の維持のみならず、地域の経済や社会全体の維持可能な発展にも重要です。農業は、単に農作物を生産するだけではなく、地域の伝統や文化を守り、自然環境を維持し、災害を防ぐような、私たちの生活に様々な恵みをもたらす多面的な機能を有しています。そのため、農業の魅力と重要性をしっかりと発信して、若い人材を地域に呼び込んでいくことが重要です。
農業をやりたいと私のところに相談に来られ、五年前に愛知県の農業大学校を御紹介した方がいましたが、最近お会いして、その後どうなっているのか状況をお伺いする機会がありました。農業に参入したけれども、収入を得て生活していくことが難しく、今でも農業経営としては成り立っていないとのことでした。
まずは農地の確保ですが、まとまった土地を確保できないとのことで、小さな土地に野菜など生産されていますが、販売ルートも確定できていないそうです。燃料や肥料など、新規就農者にとってこうした様々な情報を収集しながら、経営環境を整えて、経営基盤も整えていくことはとても大変なことだということであります。そのため、農業を支える人材を呼び込んでいくとともに、そうした方々が農業経営に必要な情報を得ながら、地域で活動ができるようにしっかりと支援していくことで、地域全体の持続的な発展につなげていくことが必要です。
このような状況を踏まえて、次世代の農業従事者を育成し、食料生産基盤を維持していくために、農業の担い手確保に向けた具体的な施策を強化する必要があると考えます。
そこでお聞きいたします。
地域農業の担い手となる人材確保の現状と今後どのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。
これで壇上の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
◯労働局長(大嵜みどり君)
労働問題におけるカスタマーハラスメント防止に関する条例の内容についてお答えいたします。
本県では、カスタマーハラスメント防止条例検討会議において、一月に条例骨子案を取りまとめたところです。
骨子案では、製造業などが集積し、事業者間取引が活発な本県の特徴を踏まえた上で、主な構成をカスハラの定義、カスハラの禁止、顧客等への配慮、防止対策に取り組む主体及び責務としています。
カスハラの定義については、顧客等からの行為、言動のうち、社会通念上相当な範囲を超えた内容や手段、対応で行われるものであり、就業者の就業環境が害されるものとしています。
また、何人もあらゆる場所及び状況において、カスハラを行ってはならないと明確に禁止する一方で、顧客等の権利が不当な侵害を受けることがないよう十分配慮をすることとしています。
さらに、防止対策に取り組む主体を、県、事業者、就業者、顧客等とし、それぞれの責務を明示しています。
県の責務としては、国及び市町村と協力し、カスハラ防止対策に取り組むこととし、その内容は、防止に向けた実効性を高めるガイドラインの作成や、情報の提供などとしています。
また、事業者では、就業者の就業環境を守るため、必要な体制の整備、カスハラを行った顧客等に対する当該行為の中止の申入れを講ずることなどを努力義務としています。
就業者では、カスハラに対する関心、理解を深め、顧客等に適切な対応を行うよう努めるなどとしています。
顧客等には、就業者に対する行為、言動や手段、態様に注意を払うよう努めるほか、事業者間取引業務等に従事する際にも、行為、言動などに注意を払うよう努めることとしています。
このほか、国の法改正等の動きを踏まえ、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるとしています。
現在、パブリックコメントを実施中であり、今後、その意見を踏まえた上で内容を固め、条例制定に向けて準備を進めてまいります。
次に、今後のカスタマーハラスメント防止対策に関する取組についてお答えいたします。
カスハラ防止対策は、県はもちろんのこと、事業者、就業者及び顧客等がそれぞれの立場で行うことが重要です。
そのため、条例制定の準備を進めるとともに、業界団体等の防止対策を支援するため、具体的な対応例などを示した、各団体共通のカスハラ防止対策マニュアルを新たに作成いたします。
このマニュアルを活用し、業種や業態、職種など、それぞれの実情に応じたカスハラ防止対策の手引を作成するよう、業界団体や事業者に働きかけてまいります。
また、専用ポータルサイトを開設し、カスハラの概念や企業の取組好事例、各団体共通マニュアルなどを情報発信することにより、企業に相談体制の整備や就業者への研修などを促してまいります。
さらに、就業者や顧客等の意識を醸成するため、ポスターやロゴマークステッカーなどを作成し、周知、啓発を図るなど、カスハラ防止に向けて取り組んでまいります。
続きまして、民間企業の人材確保、離職防止になるような奨学金返還支援の取組についてお答えいたします。
本県では、積極的に採用活動に取り組み、人材確保を図る中小企業等に対して、奨学金返還支援制度により支援しております。
本制度は、県に企業登録した上で、従業員に支給した奨学金返還支援のための手当または代理返還した額の二分の一以内を、採用から最大三年間補助するものです。
これまでに登録のあった百六社の情報は、学生をはじめとする求職者の就職先選びの参考となるよう、専用ポータルサイト、あいち奨学金返還支援ネットで発信しております。
また、制度の周知については、経済団体や市町村等を通じて行うとともに、来年度は、登録企業が企業説明会等において求職者へアピールできるグッズを新たに作成し、登録企業のPRを強化してまいります。
本制度は若者の経済的負担を軽減するとともに、中小企業等の人材確保や定着にもつながるものと考えますので、今後も多くの企業等に周知、啓発を行い、本制度の活用を働きかけてまいります。
◯教育長(飯田靖君)
初めに、愛知県が進めるキャリア教育についてお答えをいたします。
議員お示しのアプレンティスシップの制度は、生徒が実際に働くことを通して、知識や技術を身につけるだけでなく、そこで働いている方の姿を間近で見ることで、自分が職に就くことをリアルに想像をし、自分のキャリアを考える機会として大変有効な取組であると考えております。
県立高校の中には、有償のインターンシップやアルバイトを教育の一環として学びに取り入れている学校もございます。
豊橋商業高校では、IT企業と連携をして、インターンシップからアルバイト、就職へと段階的につなげる取組を行っております。この取組により、生徒はIT業界について理解を深めてから就職をすることができるので、職業のミスマッチを防ぐことも期待ができます。
また、城北つばさ高校の昼間定時制課程では、アルバイトを学びの一環として取り入れた選択科目を設けております。生徒は一年間同じ事業所で働くことができ、その経験を通して、職業観、勤労観を身につけ、自ら進路を選択できるようになっております。
また、議員お示しの介拓プログラムは、福祉、介護を目指す子供たちが、実際の職業を体験しながら学ぶことができるよい制度であり、県立高校でも二年前から募集をし、生徒が参加をしております。
こうした有償のインターンシップやキャリア形成につながるアルバイトを企業や経済団体の協力をいただき、より多くの高校で実施をできるようにし、リアルなキャリア教育につなげてまいります。
次に、県立高校における進路指導についてお答えをいたします。
生徒は自分で就きたい職業や学びたい学問を調べたり、大学や専門学校の模擬授業を受けたり、インターンシップを体験したりする中で、進路のイメージを持って、その後の個別面談で教員の支援を受けながら、実際の進路を選択していきます。
生徒たちはこうしたプロセスで進路を決めていきますが、具体的な目標や興味を持たないまま大学に進学をする生徒も少なくありません。
こうした生徒をなくすためには、将来働くという意識を育て、そのために何を、どこで学ぶことがベストの選択なのかを、子供たちが考えるような学びを実践していく必要がございます。
そのためには、子供たちが企業や大学等を見学し、実体験をできる機会を増やし、小中学校の早い段階から自分の将来の夢や就きたい職業について考え、高校では最適な進路を見つけ、人生をきちんと選択をできるよう、子供たちをしっかりと支援してまいります。
最後に、教員の人材確保や離職防止に向けた取組と、奨学金の返還支援についてお答えをいたします。
人材確保につきましては、今年度の教員採用選考試験において、志願者の増加を図り、質の高い教員を確保するため、日程を約一か月前倒し、一次試験を六月、二次試験を七月に実施をいたしました。
また、大学三年生が一次試験を受験できるようにし、早い段階からの教職への意識づけを始めたところでございます。
さらに、高校生や大学生向けのパンフレットの配布や、教員を志す学生を集めた大学での説明会で、教職の魅力を直接現職の教員が伝えるとともに、理工系の大学の研究室を訪問してリクルート活動を行っているところでございます。
離職防止に向けましては、校長と教頭が若手教員に積極的に声がけを行い、相談をしやすい雰囲気づくりに努めるとともに、昨年九月に策定をいたしました働き方改革ロードマップを着実に実行することで、働きやすい職場環境づくりを進めております。
次に、奨学金の返還支援につきましては、文部科学省が教員の指導の質の向上や、大学院生の教員志願者の新たな確保などを目的に、来年度から大学院を修了して教職に就く者を対象とした返還の免除を始めます。
また、中央教育審議会においては、学部段階の奨学金の返還支援に向けて、さらに検討が進められております。
優れた教員を確保するため、学部段階においても奨学金の返還免除の対象とするよう、全国知事会を通じた要望に加え、本県からも国への要請を行っております。
今後もこうした取組を継続するとともに、中央教育審議会の議論を注視しながら、教員の奨学金の返還支援についてどのような方策を取ることができるのか検討してまいりたいと考えております。
◯人事局長(権田裕徳君)
県職員の人材確保、離職防止に向けた取組についてお答えをいたします。
県職員の人材確保については、これまで職員ガイダンスや職場見学会などの様々な機会を捉えて、県職員の仕事の魅力や働きやすさなどを積極的に発信しているところでありますが、最近では、人手不足の深刻化が顕著となり、特に専門職の確保が厳しい状況にあると認識をしております。
こうした状況を踏まえまして、二〇二五年度実施の採用試験から、新たな受験者層の掘り起こし、さらなる人材確保に向けた取組として、事務職については、大学卒業程度を対象に、民間企業を志望する学生や転職希望者が受験しやすいよう、民間企業の採用選考などで広く利用されている適性検査、SPIスリーを活用した試験区分の新設や、土木職については、高等専門学校卒業者などを対象とした試験区分の新設などの見直しを行ったところであります。
次に、県職員の離職防止については、職員の人材育成や職場の環境整備などが重要であると考えており、愛知県人材育成基本方針に基づく人を育てる施策を通じた総合的な人材育成の推進や、職員が県庁で働くことに魅力を感じられるよう、職員のウエルビーイングの実現やワーク・ライフ・バランスの向上など、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいるところであります。
こうした取組を着実に進めていくとともに、来年度は、仕事のやりがいや職場環境などに関する職員のエンゲージメント調査を行い、定期的に状況を把握することで、職員の働きがい、組織に対する愛着の向上につなげてまいりたいと考えております。
なお、議員お示しの東京都の取組である奨学金返還支援につきましては、県職員において実施しておりませんが、今後も国や他の都道府県の動向を注視しつつ、多様な方策を取り入れながら、県職員の人材確保、離職防止にしっかりと取り組んでまいります。
◯農業水産局長(今田幹雄君)
食料問題についてお答えいたします。
県では、農林水産施策の基本方針である食と緑の基本計画二〇二五において、意欲ある人材の確保、育成を重要な施策に位置づけ、五年間で千名の新規就農者の確保を目指して様々な取組を進めております。
具体的には、県全域の就農相談窓口となる農起業支援ステーションの設置や新規就農者向けの各種研修、技術指導の実施などに取り組み、二〇二三年度までの三年間で五百七十名の新規就農者を確保しております。
こうした施策の推進に当たっては、毎年度、食と緑の基本計画推進会議を開催し、有識者や関係団体等の委員から意見をいただき、事業に反映しながら進めております。
また、昨年五月に新たに立ち上げた愛知県・市町村人口問題対策検討会議のワーキンググループでは、市町村と一緒に農林水産業の担い手確保、育成の施策について検討を行ってまいりました。
これらの意見や検討を踏まえまして、来年度から農地や販売ルートなど就農に必要な情報を集約するオンラインプラットフォームの整備に取り組み、就農後の経営サポートまでをトータルで支援してまいります。これにより、幅広い人材を呼び込み、次世代の農業従事者を育成することで、食料生産基盤の維持と地域農業の持続的な発展につなげてまいります。
◯知事(大村秀章君)
富田昭雄議員の質問のうち、労働問題におけるカスタマーハラスメント防止対策について、私からもお答えをいたします。
カスタマーハラスメントの防止は、就業者の心身の健康を確保し、働きがいを持ちながら、安心して働くことができる職場環境や、事業者が円滑に業務を遂行できる環境の整備のために、社会全体で取り組むべきであります。
そのため、カスハラの禁止を明確に示した条例で、県が強いメッセージを打ち出すことによりまして、事業者、就業者、顧客等が協力し合い、カスハラのない誰もが安心して働くことができる社会を実現したいと考えております。
条例検討会議では、委員の皆様から何人もカスハラを行ってはならないということを条例により明確に示すことは非常に大きな意味がある、また、現場の実情に即し、働く人々に寄り添い、期待に応えるような条例にする必要があるなどの意見をいただいているところであります。
カスハラ防止に向けまして、就業者や顧客等などの全ての人が対等の立場で、お互いを尊重する社会をつくり上げることを目指し、条例案を六月議会へ提出できるよう、しっかりと取り組んでまいります。
◯九十一番(富田昭雄君)
知事、御答弁ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。
私から、再質一問と要望一つ、一つずつしたいと思いますが。
まず、教育長にでありますけれども、先ほど御答弁にもありましたアルバイトについてであります。私が調べたところは八割ぐらい許可制、もしくは校則で駄目ということでありましたけれども、キャリア教育を取り組むに当たってはアルバイトを単位で認めている高校も出てきているわけでありまして、その先にアプレンティスシップもあると思いますので、前提として県立高校でのアルバイトを認める必要があると思いますが、これについてどうお考えになるか、再度お聞きしたいと思います。
要望でありますけれども、これは教育長だけで無理かもしれませんので、これは私学振興室にもお願いして、通信制高校の状況をやはり全体がどうであるかという、これからはまだまだ伸びると思います。そういう意味では把握する必要があると私は思いますが、どこにどれぐらい入学して卒業したのかどうかということも分かるようになれば、これは進路指導にも大変役に立つのではないかというふうに思いますので、ぜひその調査をお願いして要望を終わります。
以上です。ありがとうございました。
◯教育長(飯田靖君)
県立高校でのアルバイトについてお答えをいたします。
アルバイトは貴重な職業体験の場であり、職業観、勤労観や社会性を身につけることにつながることから、有償のインターンシップや生徒のキャリア形成につながるアルバイトを、企業や経済団体の協力をいただきながら、より多くの県立高校で実施をできるようにしてまいります。よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━

