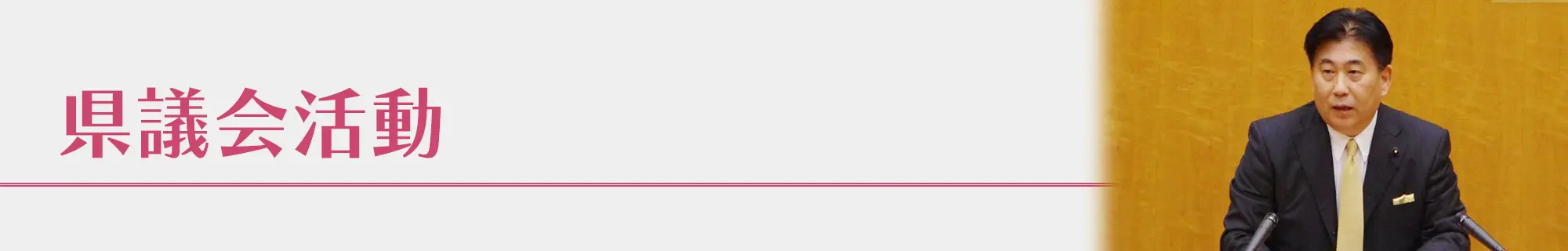

令和7年総務企画委員会 2025年3月14日
【富田昭雄委員】
災害時の備蓄をどのように市町が行っているか伺う。以前も指摘したが、直接死よりも関連死が多い事例は、能登半島地震でもはっきり出ている。そうした中で、トイレの問題が一番大きいと聞いており、東日本大震災のときも3日以内にトイレが届いたのが34パーセントしかないとのことである。備蓄の方法、どう被災地に届くかという観点から、どういった体制でどこに備蓄して、どう届くかを県がしっかりと把握しているかをもう一度確認したい。
先日、国が全体の備蓄状況の数を公表し、米やパンなどの主食、水、ダンボールベッド、トイレ、テントの数を把握したが、県として最低限必要な数を把握し、どのように届くかという体制もできていると思う。主食、水、トイレ、ダンボールベッド、テントの5項目について、現在、県内の市町村の備蓄状況及び体制、どう届くかについて把握している内容があれば伺う。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
内閣府が調査を実施した昨年11月1日現在の、県と市町村の備蓄の合計だが、まず、米やパン等の主食類は約661万6,000食、水は約162万4,000リットルとなっている。既設の便器に袋をかぶせ、し尿を凝固剤で固める方式の小型で持ち運びができる携帯トイレは県、市町村の合計で約612万8,000回分ある。
また、トイレについては食料飲料水と同様、3日分を市町村が備蓄して、不足分を県が保管して備蓄するという体制を取っているが、県の被害想定により、発災1日後に想定される避難者約71万8,000人を基礎として、これに対応して必要となるトイレは1人1日当たり5回、3日分で計算すると、トイレの必要量は1,077万回分となり、県や市町村の備蓄だけでは不足する状況となっている。このトイレについては、不足を補うために民間事業者等との協定により確保する体制を取っている。
ダンボールベッドは県と市町村の合計で約8,000セット、簡易ベッドは約1万5,000台となっている。
テントは、内閣府の調査項目に含まれていないが、県の調査によると、昨年4月現在で県、市町村の合計で約1万8,000張りのテントを備蓄している。
【富田昭雄委員】
それで足りるのかという話である。特にトイレとベッドは全然足りない気がしており、トイレトレーラーを3台購入するのはよいが、3台しか所持していない。トレーラーは、全国で81台しかない。国が調査したという話があったが、県としても調査しているのか。国の調査では、備蓄がゼロの自治体もあると聞くが、この辺りについて、しっかり県として把握しているのか。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
トイレ、トイレカー、トイレトレーラーの配備状況について、県内の市町村の状況は県として把握している。
【富田昭雄委員】
それでは、まず数として足りるかという問題がある。仮設トイレも含めて、それぞれが例えば業者に頼むと大量に持ってきてもらえる体制になっていると思うが、携帯トイレを含めた設置型のトイレのみならず、ベッドも含めて各市町村の分は把握しており、なおかつ足りるという認識でよいか。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
県として、市町村ごとの備蓄状況は把握している。市町村によってトイレカー、トイレトレーラーのように備蓄がない自治体も実際にある。特にトイレは、必要量に対して備蓄だけでは不足することが想定されるため、繰り返しになるが、民間事業者等と結んでいる協定を使い、国からも大規模地震の際には発災4日目以降にプッシュ型で支援が届くという計画をしており、県、市町村の備蓄、また民間事業者との協定、国からのプッシュ型の支援を組み合わせて確保していきたい。
【富田昭雄委員】
協定の部分の台数は、どれぐらい業者が所持しており、どのように届くかは協定の中で取り決められているか。
【災害対策課担当課長(調整・支援)】
協定の中で具体的な調達可能な台数までは定めていないが、市町村の備蓄状況や県の備蓄状況などを踏まえて、必要な数量を協定事業者に要請し、確保していきたい。
【富田昭雄委員】
台数は協定の中では把握していないとのことである。災害が起きたときに、例えば建築業者が所持している仮設トイレについて、何台所持しているか分からないが、持ってきてほしいと言い、持ってくるかもしれないが、果たして間に合うか、足りるかどうかは難しいと思う。トイレに関しては、日頃からある程度、市町村が設置型のトイレをきちんと備蓄しておく必要がある。
そうした点をきちんと県として把握してほしいと思うし、できれば台湾を参考に、プライバシーの確保を考慮すると、テントも非常に重要だと思う。これこそ、協定の部分でお願いして用意してもらわないと、在庫がなければ難しい気がする。
スフィア基準への対応も難しいところがあると思うが、最低限水と食料、トイレは3日以内に来る、そしてある程度長期になった場合はベッドやテントがあるという状況をつくらないといけない。
災害関連死が起こる点について、3か月も4か月も体育館で雑魚寝の状況が続くことや、食料もままならないことは、能登半島地震の際にも聞いた。そうした状況が続くことも、被災者は耐え忍んでいる。そういった状況が、ぜひ少しでも改善されるように、愛知県も体制を取ってほしいと思うが、防災安全局長の考えを伺う。
【防災安全局長】
避難生活を支えるための市町村の物資の備蓄の問題についてだが、指摘のとおり能登半島地震の場合、食料、簡易ベッド、災害用のトイレ等と、トイレトレーラーは補完的なもので、簡易トイレのような凝固剤で固めるタイプのものが主力になっていくかと思うが、そうした必要な物資が発災直後に不足する指定避難所、あるいは備蓄そのものがない自主避難所が発生した。
指摘のとおり、国は避難生活の取組支援でスフィア基準への対応あるいは場所の支援から人の支援への転換で、避難所外に避難する人たちも支援していくことを明確化している。したがって、市町村あるいはそれを補完する立場の県には平時から必要な物資を十分に備蓄していく必要があると思っている。
一つには、県では今回、先ほど審議された令和7年度当初予算の南海トラフ地震等対策事業費補助金の中に被災者支援緊急パッケージを新設し、車中泊避難者あるいは在宅避難者のための対策等も重点的に支援できる形で支援の部分を作っている。
そうしたものを活用し、市町村によって凸凹があるため、さらに県としても引き続き、市町村の備蓄状況を踏まえて広域的な視点から補完できる形での備蓄をこれからもしっかりと確保していきたい。そうした形で大規模災害に備えて、一つ一つしっかりと物資の備蓄に取り組んでいく。

