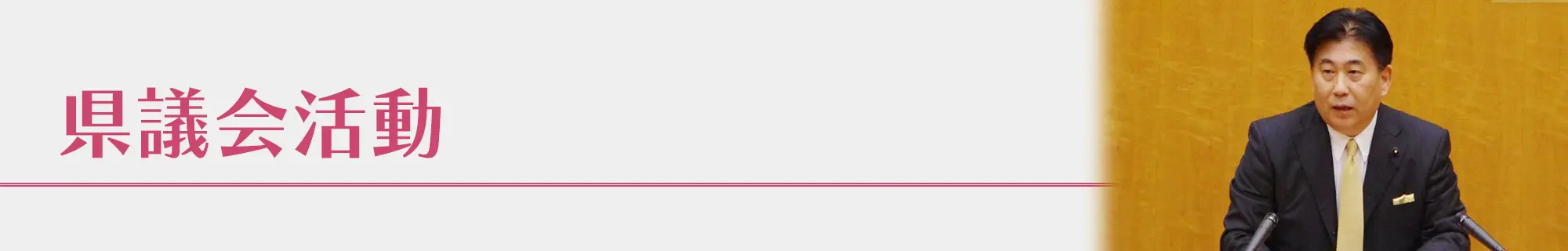

令和7年総務企画委員会 2025年3月17日
【富田昭雄委員】
近年、自治体だけでなく民間企業も人材不足であるため、職員の確保は喫緊の課題であり、新卒者を中心に人材の確保競争が激しくなっている。名古屋市において、職員採用試験で社会人枠を新設し、適性検査を導入して試験の見直しなどが行われるとの新聞記事が載っており、そういう時代かと思った。
本県も同様の採用試験を実施していると聞いているが、社会人を対象とする試験の種類と試験概要を伺う。
【人事課担当課長(人事)】
本県においても、新規学卒者に限らず多様な経験や価値観、視点を有する者など幅広く人材を確保するため、社会人採用を実施している。実施している社会人を対象とした主な試験は、民間企業等職務経験者試験、社会人試験、国家公務員総合職等行政実務経験者選考がある。
各試験の概要は、まず民間企業等職務経験者試験については、民間企業等で職務経験を有する者を対象とした試験であり、即戦力となる人材の確保を目的として2007年度から実施している。
次に、社会人試験については、就職氷河期世代を中心に、やむなく非正規雇用にとどまっている者を対象とした学歴や職務経験を不問とする試験であり、2016年度から実施している。
最後に、国家公務員総合職等行政実務経験者選考については、国、都道府県等での行政実務経験者を対象とした試験であり、即戦力として困難な行政課題に取り組む人材の確保を目的として、2022年度から実施している。
【富田昭雄委員】
近年の受験者数の状況並びにその状況を踏まえた試験の見直しの内容を伺う。
【人事課担当課長(人事)】
近年の受験者数の状況については、競争試験全体で2021年度に2,933人と3,000人を割り込んだが、2022年度に日程を1か月程度前倒ししたことにより、3,948人と対前年度比で1,000人以上増加した。その後、民間企業における旺盛な採用意欲などを背景として減少傾向となっており、2023年度では3,568人、2024年度では2,929人と推移している。
こうした状況を受け、社会人試験において、2025年度から氷河期世代に加え、育児や介護、病気などでやむなく非正規雇用にとどまっている人も受験できるよう、受験年齢について38歳から54歳までを30歳から61歳までに拡大することとしており、募集数についても前年度より増やす予定としている。
【富田昭雄委員】
本県であっても、5倍、6倍あった倍率が下がっており、試験を前倒しして少し上がったが、また下がってきており、これからもさらに下がっていくと推測される。その中で、社会人枠は非常に有効だと思っているが、今後どのように社会人採用を進めていくのか伺う。
【人事課担当課長(人事)】
社会人採用については、先ほど答弁した取組のほか、2025年度から第1回試験の事務職において適性検査SPI3を活用した試験区分行政IIIの創設や、かつて愛知県職員であった者を対象とした職員再採用(カムバック採用)選考の導入といった新たな取組を始めた。職員の確保に当たり、新規学卒者だけでなく、第二新卒などの転職希望者、本県で腰を据えて働きたい職務経験者などを積極的に採用する必要があるものと認識しており、今後も国や他の都道府県などの動向を注視しつつ、多様な方策を取り入れながら、社会人採用にもしっかりと取り組んでいく。
【富田昭雄委員】
経験豊富な人材を採用することは非常に重要であり、これからはそういう時代だと思うため、社会人枠を広げてもらい、積極的に取り組んでほしい。
もう一点、人材を確保した後の離職をどう止めるかについて、職員のモチベーションを保つためにも、人事は大変重要である。最近、民間の人と話をすると、総合職から職能型、ジョブ型、最近はスキル型まで細分化していて、一つの事業を1人で最初から最後までやるのではなく、個々に持つスキルをうまくはめ込んでいくやり方が増えていると聞いている。
また、従業員のモチベーションを上げる目的で社内公募やフリーエージェント制などを取り入れている企業もあると認識しているが、今後、本県の職員のモチベーション向上に向けた取組についての考えを伺う。
【人事管理監兼人事課長】
現在、職員の人材確保、離職防止が大変重要となっている。特に職員のやる気やモチベーション向上については、その職員の能力や経験を生かし、主体的にキャリア形成しながらしっかりと働いてもらうことが重要である。
そこで、具体的な取組として、上司と部下の対話を通じて職員のやる気を引き出すために、1on1ミーティングを実施している。加えて、職員のチャレンジ精神を尊重した庁内公募であるやりたい仕事挑戦制度を実施している。加えて、今後の職員のキャリアの形成の道しるべとなるキャリアプランを職員に示しており、これらを活用しながら計画的、効果的に取り組んでいる。
今後も、愛知県人材育成基本方針に基づく、人を育てる施策を通じた総合的な人材育成の推進やワーク・ライフ・バランスの向上などにしっかりと取り組みながら、職員のやる気やモチベーション向上につなげ、業務に当たらせていく。
【富田昭雄委員】
人を育てることが重要であり、これからは自治体を取り巻く環境が大きく変化するとともに、県だけで解決できる問題が少なくなると思う。それに対応するために専門性を持つNPOなどの様々な団体とどう連携していくかが一番大事である。そういう意味では、専門知識を持った外部の人と連携し、社会課題を克服していくためのスキルをどう身につけるかも大事なことだと思う。
従来の単純作業はさらにDXで機械化、単純化されていくため、その余ったパワーをどのように社会問題に向け、そして、現場で起きていることは何かをしっかり身につけた上で、県庁内だけではなく外部の団体と課題を解決していく力が県には必要だと思う。
自治体の中でも、市町村は現場があるわけだが、県は中間管理職のような立ち位置であるため、全体の絵を描いていくことが重要な役割だと思う。それを踏まえ、今後の職員の育成をどのように行うのか伺う。
【人事管理監兼人事課長】
人材育成については、各個人の問題もあるが、組織としても、しっかりと取り組んでいかなければならない。特に若手職員は、入庁してから育成して、長く離職せずに勤められるように、また、中堅職員についてもさらに上を目指すようにモチベーションを維持しながらしっかりと仕事に当たらせていく。
個別具体的な取組については、今後様々に検討していくが、県庁を運営するために、現在、人事交流なども国、他県、市町村、民間企業などと行っているため、そのような経験を通じた職員の育成にも努めていく。
【富田昭雄委員】
ハラスメントの種類も増え、今後さらに価値観が多様化することが予想されるなど、環境の変化はすさまじいものがあるため、それにしっかり対応できるよう、勉強会や研究会の開催による情報のやり取り、意見交換、若手の意見を聴くなど、上司から部下への一方通行ではなく、相互理解を図るための取組をしっかりと行ってもらい、人材育成に努めてほしい。

